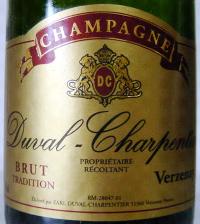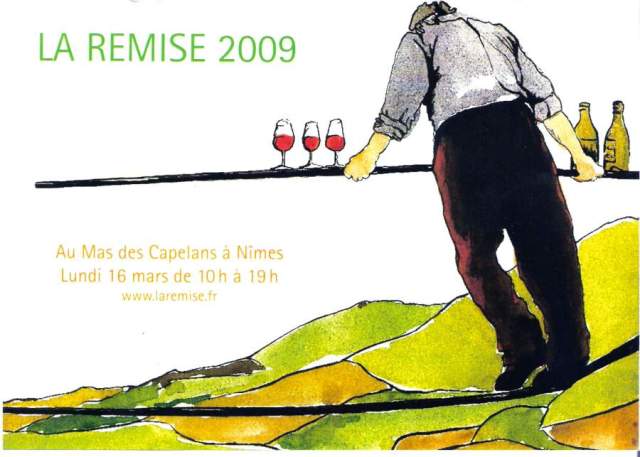Juin

Christophe Pacalet クリストフ・パカレ、ボジョレー期待の星!
パカレ・・・パカレ・・・パカレ・・・ 誰もが知っているこの名前・・・ でも皆さん、このクリストッフ・パカレ氏をご存知ですか・・・? そうです! 彼はあの有名なフィリップ・パカレの従兄弟なのです! しかも彼の叔父さんはあの偉大なマルセル・ラピエール氏! 優しくて大らかな雰囲気はまさに叔父さん譲りでしょうか?! 何でも一生懸命に答えてくれる、笑顔がプーさんのような素晴らしい方です! 彼は18歳のとき、高校卒業と共にリヨンで生化学の学校へ進学。しかし生化学の勉強はつまらない!と思い始め、料理の道へと転身。そして19歳から23歳の間、リヨンでシェフとして働き始めます!1998年までは、オフシーズン中(11月から4月)、カリブ海の島、アンティーユという島でシェフとして働き、5月から9月の間は、ラピエール氏の収穫を手伝いながら、ワイン醸造を学びます。(何てラッキーな・・・・!) この頃、ちょうどクリストフはアンティーユで自然派ワインを紹介し、売り始めます! 『皆自然派ワインを気に入ってくれて本当に嬉しかったな。そのころアンティーユでワインを購入してくれていたお客さんから『何故シルーブルやブルイィーは自然派で美味しいワインがないのか?』と聞かれ、私はハッとしたんだ。皆こういうワインを求めている。じゃあ自分で造るしかない!と思って自分のドメーヌを設立することを決心したんだ。ちょうどその頃私は今の奥さんと出会い、島へ戻るか、フランスに残るか迷っていたからちょうど良かったんだけどね!』 と言う事で1999年に彼のファーストヴィンテージが誕生しました! *** ここでちょっとした『ボジョレー・レッスン *** 『ボジョレー地区で最も綺麗な区画は Côte de Py の丘に在る区画なんだ。 そして平均45hL/Haの収穫量が最も美味しいボジョレー・ワインを生み出すんだ。でもここでは植え付け密度が10000株/Haの上、ガメイが昔のように売れないので、根を切りなさい!とINAOに言われるが、根を切ればブドウ木の競争率が低くなる。そうするとブドウの実が逆に増えてしまう。 矛盾していると思わないか?』 確かに・・・・ *** そしてブドウ品種について! *** 『ガメイ品種と最も相性の良い土壌は、まさにボジョレー地区の、やせている花崗岩質の土壌なんだ。 しかもガメイはつる植物なので硬い岩の上でも根を張れるんだ!』 *** ワイン造りについてはどうなのでしょう? *** 『私は自分で選んだ区画以外のブドウには興味がありません。樹齢が古く優良な区画を選び、健全で理想的なブドウを収穫するため、栽培者との間にぶどう栽培における仕様書を作成したうえで、契約をしています。どんなに天候が悪く、収穫量が低くなってしまっても、他のブドウは購入しないんだ。それだけ自分が選んだ畑のブドウが好きなんだ!』 と笑顔で教えてくれるクリストッフ! 『私は毎年同じ区画のブドウは同じ樽を使って醸造しています。その際、残糖が15gr/Lの時点でバリックへ移すと、天然酵母が再度元気になり、良い発酵が再スタートするのです。醸造の時、大樽を使用するほうが楽なのだが、バリックの方がより多くの味わいが引き出され、複雑なアロマに仕上がります。そして熟成中、木樽で寝かせると、オリがきれいに下に沈むのだが、ステンレスタンクを使用すると、タンク内で静電気が常に動くため、オリが舞ってしまうので私は使いません。ガス抜きはアルゴンガスという、希ガス(不活性元素)の中でも最も空気中に占める割合が大きいことで知られるガスで行っています。窒素よりアルゴンを使用したほうがアロマが飛びにくいと、ジュル・ショベ氏が発見したのです。そして仕上げに、樽の底部のみ粗いフィルターをかけて終了です!』 最高にナチュラルなワインを造ろうと手掛けているクロストフ。醸造中、色々と手を加えるのが苦手! 『私は色素やタンニンを抽出する事は全く考えていません。むしろタンニンの繊細さを引き出すことが重要だと思っています。』 *** 2008年ヴィンテージ *** 『冬がとても寒かったので、澄んだワインが出来ました! しかし4月には雹がかなり降り、通常の生産量の2/3が被害にあってしまった・・!』 AOC Beaujolais Villages 07 素晴畑はクリュ・ボージョレーの直ぐそばにある畑で収穫されたブドウ。 フルーティーで飲みやすく、酸味と糖分のバランスが綺麗な一品です! AOC Chiroubles 07 とても濃厚なのに飲みやすい! フルーティーで軽い後味が残り、完熟いちごを思わせるような、甘い香りが特徴的! AOC Chiroubles 08 去年に比べアルコール度数も低め(11.5度)なので、とても軽くて飲みやすいです。 果実身と天然ガスを保つ為、大樽で熟成したキュべです! AOC Côtes de Brouilly 07 なめらかで繊細。綺麗なタンニンが印象的です! AOC Moulin […]